|
|
|
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「08年最後の作業」
|
2008. 12.
20 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「08年最後の作業」2008・12・20(土)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、早川、野本、窪田、世良田、小椋、竹内、稲岡、吉田。川路、尾崎、池田、高橋、
稲岡(喜)、原。
てくてく3名、安田、泉。
|
|
まず最初にお詫び。前号の宛名欄にいろんなグループを入れてしまって失礼しました。お許しください。
9時作業開始なのに、8時からスコップをにぎっている世良田さん。
「今日は残業できないから、早出・・・」。 そうだ。今日は本年最終日であり、まだ土入れが終らない面積が相当残っている。高田さんは「今日の午前中で終るのはとても無理だ。」と広言している。
8時半には5名が集まり、9時には衆議院議員 泉 ケンタ氏も現れて、土を運ぶ。広い竹林に汗と笑いが飛び散った結果、11時に全て終了した。
昼からの忘年会は夫婦同伴での参加が3組あり、うれしかった。我々の竹林ボランティア(里山保全)が家族に認められるのはなにより大切なことだ。 |

|
|
|
|

|
|
まず臨時総会。議題 特別会員の件、新入会員の承認の件 いずれも満場一致で承認。
その後は来年の目標を語り合った。
連携していく団体―京都ニシワイズメンズクラブとFoE京都
舞台施設の半恒久化工事の検討。
タケノコ発送の箱、パンフレット、竹炭づくり、原木シイタケの増設。
水琴屈(竹濤庵に、小椋・世良田さんをリーダーに)。
竹工芸(辻井夫人をリーダーに)。
枝豆栽培の実験(野本さんをリーダーに)。
会計担当の交替 -世良田さんに。
来年は1月10日(土)がハツデ。この日の趣向は野本さんが考える。まず焚き火から入るそうだ。
火を焚いて みな縄文の 貌となる 丸山哲郎
みなさまよいお年をお迎えください。
杉谷 保憲
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|

|
|
|
|

|

|
|
|
|

|

|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「21世紀点描(1)」
|
2008. 12.
17 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「21世紀点描(1)」2008・12・17(水)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、早川、野本、窪田、錦織、世良田、小椋、竹内。稲岡(喜)。
今朝まで小雨、土が湿っていてすくいにくい。タケノコに粘土質の土がいいのだが、そんな土はいよいよやりにくい。
今日は中央竹林の土入れができた。 残すは乙女の丘から南へ、シイタケ園までであるが、
それでも かなりの面積である。
果たして本年最終日(土)の作業がどうなるやら・・・。
今年も世間は騒がしかった。3人の日本人がノーベル賞を受けたのは朗報であったが、他にはグッドニュースを思い浮かべられない。親がわが子幼児を殺すのにはやりきれなかった。
最大のニュースはアメリカ大統領選挙であろう。敗れたブッシュ現大統領が数日前イラクを訪問し、記者会見席上でイラク人記者の一人から靴を投げつけられた。
いささか礼を失する行為であるが、 このニュースには世界中の人が無理も無いと記者に心を寄せた。
イラクに大量破壊兵器が隠されているとしてブッシュはイラクを攻めた。フセイン大統領を処刑し、数十万のイラク国民を殺した。フセインが自国の石油のドル取引を止めていたのを、ブッシュはイラクを占領して、これを復活させた。戦争の目的をいろいろ挙げたが。ドルが主眼目であったのである。
そしてブッシュは、大量破壊兵器は無かった、CIA情報が間違っていたと後悔の弁を述べた。蹂躙された側は靴を投げつける抗議が精一杯であった。
テロとの戦いと銘うって、中東を殺戮の大陸にした。なぜテロをするのか考えたことがあるのだろうか?
ブッシュ政権下で鳴りを潜めていたアメリカ国民は道徳的な責任を感ずべきである。ブッシュに従った各国の首脳も反省の弁を述べるべきだろう。このまま頬被りするような人には、国の未来や国際平和を語る資格は無い。
アメリカ文明は輝かしい時期があり、世界の民衆が羨望の眼差しをそそいだ。しかしこの文明は自制の力を持たず、政治は暴走した。グローバリズムという経済は世界中に極端な貧困を作り出した。
21世紀は8年たったが、不幸な始まりであった。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「土の文化遺産」
|
2008. 12.
13 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「土の文化遺産」2008・12・13(水)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、早川、野本、窪田、世良田、小椋、竹内、稲岡、吉田。高橋。
てくてく1名、ワイズメンズクラブ2名。
|
|
高田さんの見通しによれば、土入れが今年中(来週水、土の作業日)に終ることは無理になってきたそうだ。もう少しの面積であるが、まあ、仕方ないか。
今日はいい話を聞いた。来週の忘年会には夫婦同伴の出席が多いそうである。いい傾向だと思う。
今日はこれから私は大阪で、高校の同窓会に出席するので、竹林日記をつくっている時間が無い。
来週水曜日の京都新聞洛西版「竹想譜」の予定原稿があるので、これを転載する。
|

|
|
竹想譜「土の文化遺産」 杉谷保憲
竹林にはワラが敷きつめられ、その上に土が薄く広げられていく。この土入れと呼ばれる客土作業は11月から12月にかけての仕事で、重労働である。田んぼでは稲刈りも田植えも機械化されたが、竹林の作業には機械の導入がむずかしい。竹は背高であり、硬いから機械が動きにくい。だから相変わらず一輪車で土を運んでいる。竹林の斜面で一輪車を動かすのは体のバランスをとることが大変、へとへとになってワラの上の腰を下ろし、しみじみとタケノコ畑の土について考える。
なぜ今もこんなしんどい労働が続けられているのだろうか。全国のタケノコ産地ではどこにもこんな土壌づくりをしているところはない。近辺ではどうか。当会会員の情報によると、山城タケノコと呼ばれる木津川市ではワラ敷きも土入れもしないそうだ。伏見ではかつてはワラを敷いていたが、今は土入れだけにしているという。各地の栽培法は簡素なようである。
とすればこの丁寧な土壌づくりは京都市右京区の塚原から大山崎の間、つまり西山一帯だけである。この地方の竹林はワラと柔らかい土によってぬくもりいっぱいである。
もともとモウソウチクは中国・江南からタケノコという食品を得るために移植されたものである。
西山一帯は明治・大正時代にかけて、京・大阪という大都市をひかえたタケノコ生産地であったから労働集約的なやり方でも成立したことだろう。そして百年の歴史を重ねてきた。
また面白いことに、農業は土を掘り返すこと、つまり耕すことから始まっているにもかかわらず、タケノコ畑の土壌はワラと土を重ねることだけで、決して耕さない。
現代の少子高齢化の条件ではこの重労働を続けることは困難になっており、輸入タケノコと競合させられて採算もとれない。しかしそれらを乗り越えて、なお莫大なエネルギーが注がれている。それはタケノコの究極の味を追及しているからにほかならない。(現代では環境問題として新しい観点がでてきているが。)西山の土質とこの豊かな土壌は農業の文化遺産である。
そう考えると再び元気が回復する。西山のタケノコは今、深い眠りに入っている。その上にそっと布団をかけるように土を撒いていく。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「竹カッフェ」
|
2008. 12.
10 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「竹カッフェ」2008・12・10(水)曇り
参加者 杉谷、高田、西村、野本、窪田、錦織、世良田、竹内。稲岡(喜)。
昨夜雨が降ったようだ。長靴姿である。
土入れが今年中に終るかどうか、が会話を引っ張る。今年の作業日は残すところ3日だけである。頑張れば土入れが終るかもしれない微妙なところであるが、例年1月の末に終っている。
新人の世良田さんが「ヨーシ、残業してでも、除夜の鐘を聞きながらでも期限内にアゲマしょう!」と言う。久しぶりに企業言葉を聞いて一堂が笑い転げた。
昨日「竹カッフェ」に山本さんと出席した。これは京都府地域力再生プロジェクトが主催する会議で、府下の竹関係の団体から80名ほど参加していた。
竹が日常生活に使われなくなって久しい。今は庭園の竹垣、茶・華道の道具など限られてしまった。
今回も伐採竹の利用法が議論された。
粉末にする、竹炭にする、竹工芸を興すなどここ数年話し合われているが今一歩乗り越えられないもどかしさがある。竹が経済性をつくれないのである。
新しい観点、竹炭にして畑に埋め込む、バイオエタノールをつくる、竹のCO2吸収力を利用するなどの議論も展開された。これも宝の山に見えるが、まだ掘り当てることができない。
私たちは竹を素材として利用するのにはまだ時間がかかるとみて、竹林という“場”を利用することから始めた。それが竹林コンサート、原木シイタケの栽培、花壇などである。これらも経済性を求めるわけにはいかないが、環境問題としては有意義である。
“場”として利用しているのは向日市の「かぐやの夕べ」があり、舞鶴市のふるさと大浦というグループが検討しようとしている。
竹素材の利活用はなかなかうまくは運ばない。
私たちは今年習った竹炭作りを来年は本格化させたい。先行する諸団体のこれまでの経験を学んだ上で、CO2吸収の面を新らたに開発したいと「竹カッフェ」の議論を聞きながら思った。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「ダル」
|
2008. 12.
6 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「ダル」2008・12・06(土)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、早川、野本、窪田、錦織、小椋、稲岡、吉田、
辻井、世良田。川路、尾崎、高橋、原。
てくてく2人、ワイズメン3人。
|
|
今日は応援部隊があり、しんどい土入れ作業だが心強い。竹林面積の半分が終っただろうか。
ニュースが暗い。首切りや就職の内定取り消し・・・サギに殺し・・・。こんな世情の時期に、薄っぺらな首相では困ったなあ。ホテルのバーに夜毎出入りするのをやめろとは言わないが、国民の気持とは離れている行動だ。
朝刊の記事に、日本ハムのダルビッシュ有投手(大阪出身)が大阪の羽曳野市の児童養護施設を訪れた、とある。子どもから「阪神タイガースにいつ来てくれますか?」と質問されて、「まだ先のことなので分りません」と苦笑しながら答えたという。
|

|
|
この質問した子どもの気持がよくわかる。私もタイガースの来年の投手陣が心配なのだ。しかしダルビッシュがすぐに阪神に来るわけは無い。い期待ではなく、なんとしても自前の選手を鍛え上げていかなければならない。
今は過去50年の延長上に未来の日本を描くことはできない。日本にとっての50年間の親分がコケル時で、親離れの時期に立っている。首相はしっかり国民の気持を把握して立ち向かってほしい。浮かれていることはできないのだ。心配だ。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「男女共同参画」
|
2008. 12.
3 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「男女共同参画」2008・12・03(水)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、西村、窪田、錦織、世良田、小椋、竹内。稲岡(喜)。
暑くも寒くもなく風もない。体を動かすのには最高にいい条件だが、実際には体を少し動ごかしただけでヒーヒー言っている。今日も土入れが続き、一輪車を動かす。竹林はほとんど斜面であるから、上り下りに力が要るし、体のバランスを保つのが容易ではない。休み休みながらも少しは進んだ。
NPO法人になってから半年がたつ。なにも変わりはないが、諸官庁から大学からアンケートがたくさん来るようになった。今日は内閣府 男女共同参画局から、「NPOで活動する女性へのアンケート」である。
共同参画とか協働参画とか漢字に少しの違いがある。多分いろいろ定義がされていることだろう。だれか相違について教えてほしい。
昔、学生運動の中で、「男女」という言い方は差別である、なぜ男を先に置くのか、女を先に言うべきだ ――つまり「女男」とするべきだという主張を聞いたことがある。
私は、どちらかを先にすればどちらかが後になるから、これは差別意識から出たものではなかろうと反論したら、それなら女男でいいではないか、といわれた。
「夫婦」はフウフと読むが、昔は「みょうと」それが変化して「めおと」と読んだ。これは「女男(めおと)」あるいは「妻夫(めおっと)」が語源だと言う。
江戸時代までは「女夫」「妻夫」と書いたそうである。
もっと古くは「妹背(いもせ)」である。この場合は妹が妻で、背は夫を表す。
古い日本の表現は女を先に言うのだ。あの学生運動の女闘士が言ったことは間違いではなかったようだ。
男女共同か協働か、男女の順番もむずかしいが、後半のキョウドウに焦点を置いて、ともかく助け合って仕事をしたいものである。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「土の文化遺産」
|
2008. 11.
29 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「土の文化遺産」2008・11・29(土)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、早川、野本、窪田、錦織、世良田、稲岡。
川路、尾崎、池田、原。てくてく1名、ワイズメンズクラブ3名。
|
|

|
日も土運びの一輪車が竹林の中を行き来している。全面に敷かれているワラが少しずつ土に覆われて、その土の面積が少しずつ広がっていく。
休憩も2回とるが、冗談口も少ない。会員はおおむね高齢で、動作は緩慢になった。てくてく来た青年の軽快な動きが目立つ。
前回から土について考えている。
ワラ敷きと客土(土いれ)という労働集約的な土壌づくりは今やほとんど姿を消した。
京タケノコ・乙訓タケノコと呼ばれる産品をつくる京都式軟化栽培法は時代に合わなくなった。
|
|
ただこの西山(右京区塚原から大山崎までの桂川右岸沿い)だけに残っている。
山城タケノコと呼ばれる宇治川、木津川沿いはどうであろうか?ここによく来る木津川市の青年は、木津地方ではこんなことはしていないと言う。伏見区に住んで、自らタケノコ作りを始めるに当って、当会に勉強に来ている辻井さんは「古い住人から聞いたことだが、かつてはワラを敷いていたけれども今はそれをやめた。現在は土をかけるだけにしている。」と言った。
全国の他の地方は言うに及ばない。
タケノコづくりのためにこんな重労働はもう無理なのだ。
私たちは最初に“伝統的栽培法を継承する”と掲げた。そして伝統に忠実に栽培して6年目になる。
そして考える。こんな土壌づくりは今や、労力の面でも採算の面でも全く成り立たないが、うまずたゆまずこの土壌作りをするのは、唯一タケノコの究極的な味を追及しているからだといえる。京タケノコ・乙訓タケノコの味には恐ろしいほどのエネルギーが注がれている。
この土壌は農の文化遺産と考えるべきであろう。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「結婚願望」
|
2008. 11.
22 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「結婚願望」2008・11・22(土)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、野本、窪田、錦織、世良田、小椋、稲岡。
川路、尾崎、高橋、稲岡(喜)。
京都ウェストワイズメンズクラブ3名(松本、星野、牧野さん)。
土入れ。敷きわらの上を尺取虫が進むように土がかぶせられていく。今日はワイズメンズクラブから3人の参加。松本さんは一輪車で土入れ作業、星野さん、牧野さんは枯れ竹の焼却作業。当会会員と和やかな交流である。
|
|

|
またも孫の話。2歳2ヶ月の女児はよたよたと30メートルぐらい走るが、三輪車には足が届かない。おしゃべりは単語を二つ三つつなぐ程度である。数や文字の概念はまだ無い。
絵本が好きである。竹取物語を読んでやった。
「お爺さんは一本の光る竹を見つけました。」
窓の向こうの竹林を指差して「タケ、タケ」という。
「かぐや姫は大きくなって、5人の男の人から結婚してくださいと言われました。」
|
|
絵本を閉じて、いつものように公園の散歩に連れ出した。
ひょこひょこ歩いている姿は可愛らしい。そこへ顔見知りのおじさんが通りかかった。
孫が話しかけている。
よく聞いてみると「結婚してください!」
おじさんはその意味が分らない。私は仰天して、急いでわけを話した。
彼は言う。「お宅のおジョーちゃんは2歳にしてもう結婚願望があるのですか・・・」
杉谷 保憲
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「軽いノリ」
|
2008. 11.
19 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「軽いノリ」2008・11・19(水)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、西村、野本、窪田、錦織、世良田、小椋、辻井。
「寒うなりましたなあ」口々に言い合う。晴れてはいるが気温は下がった。
竹林では施肥が終り、土入れが始まった。これからが一年のうちで最も重労働の季節となる
家の郵便箱に日本共産党からのチラシが入っている。
「バラマキ一瞬 増税一生」というジャック。うまい。
給付金2兆円が選挙めあてに全国民に配られるが、3年後からは消費税の10%へ引き上げがあるので、全国民の負担額は毎年13兆円になることへの警告文である。
ジャックづくりは小泉元首相もうまかった。後継の安倍首相が突然に辞任表明したときに発した言葉。
「人生にはいろんな坂があるが、マサカというサカもある。」
ジャックは軽いノリが面白い。ノリは論理や整合性を必要とせず、キャッ、キャツとなるかニヤリとさせられて、それでお終いである。
環境問題がこんな軽いノリでしのげると楽であるけれど。
12月7日(日)13時~バンビオ1番館で環境問題のシンポジュームがある。私もおしゃべりに出る。そのため「竹の学校」の紹介を写真アルバムとして小椋さんがパワーポイントで制作している。面白い作品になりそうだ。
二人でその作業をしたために「竹林日記」をつくることを忘れてしまい、今回は一日遅れの配信である。
「NPO法人 竹の学校」になってから記録を大切にしている。このパワーポイント作品や第2回竹林コンサートのビデオ(田中企画制作)や小生の論文「竹林整備の諸相」(Bamboo
Juarnal
30)と続いている。
来年はこの面に一層力をいれるとともに、長年の課題、タケ材に有効利用を具体化させたい。
そんなこんなを語り合う忘年会は12月20日(土)昼食会として「穂積」で。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「竹の実」
|
2008. 11.
15 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「竹の実」2008・11・15(土)晴れ
参加者 杉谷、高田、野本、窪田、錦織、世良田、小椋、稲岡。高橋。
てくてく1名。
ユンボが崖を崩し、土とり作業をしている。朝8時から動き、数箇所で土を作り12時半に終了したという。窪田さんと小椋さんがつきあった。
今日は面白い話しを聞いた。竹の実についてである。鳳凰が食べるとのことだ。
鳳凰は想像上の鳥だ。金閣寺、宇治平等院の屋根のうえにましましている。1万円札の裏にデザインとしてあるから見ていただきたい。
竹の花は60年一度とか100年に一度咲くといわれる。だから実がなるのもその間隔であろう。インターネットには写真があり、竹の実は赤い。
鳳凰の話しの元はインドで、中国には紫禁城に彫刻があるという。竹には雌雄が無いが、鳳凰にはオス、メスがあるそうだ。
竹取物語にある“竹が光って、そのなかならかぐや姫が生まれてきた”話も突飛な想像であるが、鳳凰が竹の実を食べに来る話も神々しいことである。
つまり鳳凰は60年に一度は竹林に舞い降りてくるのであろうか?
仲間たちよ!その日を待とうではないか。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「初!シイタケ」
|
2008. 11.
12 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「初!シイタケ」2008・11・12(水)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、早川、西村、野本、窪田、錦織、世良田、小椋。
静かな竹林に絶え間なく体を動かしている人々。今度の土曜日にバックフォー(ユンボ)を迎え、作業をしてもらう予定になっているが、ユンボが土掘りをしやすいように整備が続いている。
竹林では上を見上げることは少ないが、今日は雲ひとつ見えない空だ。
シイタケが採れた。15個ぐらいあっただろうか。
これから数日は晴れるとの天気予報なので、水をかけておこうと近づいたら、なんと来年の秋だろうと思われていたシイタケがすでに開ききったものも含めて、姿を多数みせている。シイタケをもぎ取ろうとするが肌触りがやわらかく、すぐに取ってしまうのが惜しい。 |
|

|

|
|
|
|
去年12月9日、窪田さんと私は大阪で「原木シイタケと銘酒の会」に出席した。その席で菌床栽培シイタケとくらべて原木栽培ものがどんなに優れているかと、奈良県吉野の青年が力説した。私は感動した。
竹林はシイタケ栽培の適地であることは知っていたので、高槻きのこ園から50本の原木を買った。原木が到着したのは今年4月3日のことだったが、実際に菌うちしたのは5月1日であった。菌うち作業が遅れたので、シイタケが出るのは1年後の秋になるものと思い、時折水をかけていた。 |

|
|
|
|
それが予想よりはるかに早く、半年後にシイタケが出たのである。私は喜んだ。みんなの顔もほころんだ。
春にタケノコ、夏にキヌガサタケ、秋にコンサートそして冬にシイタケ。その上に花壇の花々。
一年中、竹林はミドリの姿のままで、傍目には変わることはないが、中は変化に富んで、心を和ませてくれる。持ち帰った初物のシイタケは焼いて醤油で食べた。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「雅楽に涙する人」
|
2008. 11.
1 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「雅楽に涙する人」2008・11・1(土)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、早川、野本、世良田、稲岡。稲岡(喜)、原。
てくてく2人。
ツワブキの黄色とコンギクの紫色が目に沁みる。秋が深まってきた。竹林の中の花壇が楽しめるようになったので四季の変化を感じられる。
ワラ敷きなどユンボを迎えるために、今日は細かい準備である。
「ワラ敷きならできる」と言って、てくてくから一人が参加してきた。気分が乗ってきたのだろう、久々の登場である。嬉々としてワラを運んでいる。
付き添いの富島さんが現れる。
「竹林コンサートには車椅子の人の同伴で来られましたね。」と私。
富島さん
「ええ、一人だけ連れてきました。あの子は音楽が大好きなので――。
最後のサンタルチアでは、本人は持っていたハンカチをマイクにみたてて、大きな声で“サンタ~ル チ~アと絶叫していました。
その前の雅楽ですが、あの子は聞きはじめから泣き出すんです。“おばあちゃんが死んでしまったア”と。
あの子のお婆ちゃんが亡くなったのはずっと前のことですけれどねえ。どういうことなんでしょうね。」
私は驚いた。「雅楽の最初の曲、竹林楽は葬送に使われていたと言われていますよ。」
「はあ・・・やはり・・・。あの子はこと音楽に関しては天才的なところがあるんですよ。」
山下清とか昆虫のショウちゃんとか、絵を描かせると天才といわれた人を見てきた。彼らは身体能力の点では弱いけれど、感覚、感性は常人以上のものを持っている。
同じことが音楽の世界にもあるのだと始めて知った。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「ナニコレ?」
|
2008. 10.
29 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「ナニコレ?」2008・10・29(水)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、早川、野本、窪田、錦織、世良田、小椋、辻井。
竹林は道路より10メートルぐらい高い。去年までは、ワラを積んだ車は道路で下ろした。そのワラを私たちが運び上げたのだが、重労働であった。
身障者が車椅子のまま竹林に入れるようにしようと、狭い坂道をつくった。その道幅を高田さんがムキニなって広げた。そして今年、ついに軽トラック(2トン車)なら昇ることができるようになった。
ワラを積んだ車が道路から竹林への坂道を上がる。今年は私たちが担ぎ上げる必要は無くなった。まるでチベットへ汽車で行けるのと同じだなあと思った。
そして今日もワラ敷きが続く。
妻が入院している間、娘と孫娘(2歳)がわが家にしばしば訪れて、家事をこなしてくれた。私が孫のお相手をする。2歳を過ぎると脳内の細胞が分裂・増殖するらしい。単語をつないで言葉を使うようになる。
孫は「コレ何」を連発する。
これは鉛筆。これはめがね。・・・答えていくのも閉口だ。
一緒に風呂に入ったときである。石鹸を使っていた私に「ナニコレ?」ときた。
私の一物を指差している。
私は応えなかった。しかし彼女は執拗に「ナニコレ?」
やむをえない。「これ、オチンチン」
納得したのか、視線は逸れていった。
ほっとした。
そして私は寒々とした一物に温かい湯をかけた。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「慣れない一週間」
|
2008. 10.
25 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「慣れない一週間」2008・10・25(土)曇り
参加者 山本、杉谷、高田、早川、窪田、錦織,世良田、小椋、稲岡、吉田。
川路、高橋、稲岡(喜)、原。
今日の作業は主としてワラ敷き。全体の70%に敷きつめられた。竹林が穏やかな景色になった。
竹林コンサートから一週間が過ぎた。疲労がようやく抜けたようだが、その一方で慣れない時間を過ごした。平素、褒められることも無いのに、会う人ごとにコンサートがよかったと声をかけられて、かえって疲れる。よかったとすれば、出演された人たち、陰で支えてくださった人たちのお力の結果だ。
私のメールアドレスに入った感想文を二つ紹介する。
「(皆さまは) 竹林を育てるだけでなく、子供たちをも育ててくださってる、素晴らしい。本当にありがとうございます。本当に感謝申し上げます。」
「昨日友人に会いました。私の友人は、
「ニューヨークに10年間住んでいた友達と竹林コンサートにでかけたが、その人が、
『これこそ日本だ。あなたは本当にいいところに住んでいる』と感激してくれた。」と言っていました。
私の友人自身も「とても楽しく、すばらしいコンサートだった。ニューヨーク帰りの友人に、竹に耳を当てて風の音を聞いてご覧といったのよ」と竹林の雰囲気を満喫していたようでした。本当によかったですね。
多くの方に感動をもたらした竹林コンサートだったと思いました。」
会場でアンケートをとったが、そこにも貴重なご意見があった。
竹林に来られた方たちは何がしかの感想を抱かれたようである。
一年目よりは二年目、二年目よりは三年目・・・少しでも多くの人が地球環境に思いを馳せる--――それが竹林コンサートの役割だろう。
それにしても慣れない一週間だった。
これから重労働の秋、土入れのシーズンを迎える。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「第2回竹林コンサート舞台裏」
|
2008. 10.
22 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「第2回竹林コンサート舞台裏」2008・10・22(水)曇り
参加者 山本、杉谷、高田、早川、西村、野本、窪田、錦織、世良田、小椋、辻井。
竹林コンサートは18日(土)に無事に終った。すでに舞台は撤去され、今日は座席(竹のベンチ)の解体をし、次のワラ敷きのための準備である。
その合間にコンサートの反省会を開いた。
コンサートは外では好評であるが、内部では疲労困憊。しかし前向きの意見がつづく。次回への参考になる材料が多かった。
それとは別に二つの話を記しておきたい。
冒頭に私が挨拶に立った。主旨を話し終えて、頃はよし、笑い話で挨拶をまとめようとして、舞台の袖に目をやる。そこには演出も演出助手もいない。普通、時間を知らせる人が居るのだが、誰もいないとは!
これはオカシイ。一瞬、判断をつけかねて、予定していた笑い話のネタを忘れてしまった。しまらない結末になった。
その時間、演出さんは雅楽のメンバーにかかりっきりであったという。冷や汗さんど。というのは道具と衣装を積んだ車の到着が遅れたので、雅楽の演者たちは出番を控えて弱っていたそうだ。てんやわんやの楽屋裏である。
予定より遅れたが雅楽が始まった。
舞台に優雅な舞いが繰り広げられる。衣装が竹林に映えて、悠久の響きを伝え、千年前に観客を誘う。まるでなにごともなかったように
もうひとつの話し。
今回、身体障害者の観客のために車椅子歩道をつくった。しかし私たちの資金では限られたことしか出来ない。もっとバリアフリーにしたいが資金不足で思うようにできない。そこで来年のために歩道用の板などを購入する費用を募金でまかなおうというわけである。募金額は3万円を心積もりにしていた。
今日の報告によれば、目標を超えて5万円集まったという。観客の心の温かさに私は目頭が熱くなった。
市役所の環境政策推進課を訪れた。課員から千円札が入った封筒を渡された。その話はこうである。
社会福祉協議会の高位の人がコンサートを見に行った。会場で募金箱に100円を入れた。帰宅して奥さんにコンサートの話をし、身障者募金の話もした。
すると奥さんに叱られた。貴方は100円しか募金しなかったのですかと。
持ち合わせが100円しかなかったのでと説明したが、奥さんは聞き入れない。
このミスター社協さんは千円札を市役所に持参して、頭を掻いて夫婦の会話を紹介したという。
私たちの社会は冷たい風にさらされることも多いが、こんなに思いやりが厚いところもある。たくさんの教えと温かい志を得た。
皆さま お疲れ様でした。こころから感謝申し上げます。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「雨女と晴れ女」
|
2008. 10.
15 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「雨女と晴れ女」2008・10・15(水)快晴
参加者 山本、杉谷、高田、西村、野本、窪田、錦織、世良田、小椋、辻井。
稲岡(喜)。
竹林コンサートの会場は99%整った。プログラムも刷り上り、杖もプレゼントの品もできた。それでもノコギリ、金づちや研磨の音が休み無く響く。みんな“納得するまで”やるという姿勢だから終わりが無い。午後も作業が続いた。
会員のうち平素作業に参加できない条件にある方、
社長業に手をとられっぱなしの荒木さん、島田さん。療養中の濱村さん、熊谷さん。土・日は野球審判に明け暮れる岸さん。
18日はなんとか都合をつけて竹林にお越しのほどを。
残るには天候の心配である。
去年は本番の前日が大雨だった。それが当日の朝、ウソのように晴れ上がった。私は開会の挨拶でテルテル坊主の話をした。
昨日は晴れの予報(週間予報で)であったのに雨に降り込められ、寒かった。去年のことを思い出してしまった。
18日の予報は晴れであるが、もし昨日のようなことになるとてんやわんやになる。
女心と秋の空というから、変わりやすい時期だ。何が起こるかわからない。
「雨女(あめおんな)」という言葉には風情がある。長い髪の女が雨に打たれているさまを思い描く。幽霊か妖怪にも通じて、想像力を刺激する。
それに比して「晴れ女」は健康的な印象だ。血色がよく生活力があり、颯爽としている。どうも作品にしにくい。
私の知り合いに強烈に「晴れ女」を自称しているひとがいる。どこに出かけても出かけた先は晴れるという。「外国旅行しても、先ほど前まで雨であったのに私が現れると晴れてしまう」というのだ。こうなると魔法使いである。
「東南アジアの雨期に旅行されたら如何か・・・」と私は口に出しかけたが思いとどまって、コンサートに招いた。魔女も「曇りのち晴れ女」も、会場に来ていただく人は「晴れ」を担いで来てほしい。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「岡田阪神監」
|
2008. 10.
13 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「岡田阪神監督」2008・10・13(月・祝日)晴れ
参加者 杉谷、高田、早川、窪田、錦織、世良田、小椋。
水・土の出動日以外に近頃、月曜日も出動して非公式に作業をしているようなので、私も竹林に行ってみた。快晴の下、6人が集まって、私を含めた7人が働いた。竹林コンサートを控えて、それぞれが気になるのである。それも11時半を越えて正午を過ぎてまで。
竹林コンサートの準備にはあと一回(水曜日)が残されているだけである。かつて野本さんが言った言葉がある。「お客さんが来る前は家の内外を掃除する。これは日本人の特性ですかねえ。」
阪神タイガースの岡田監督が辞意表明。ペナントレース2位なのだから、常識的には辞めることはない。
しかし彼の論理は、13ゲーム(7月)離していて逆転されたことについては誰かが責任をとるべきだというのである。
それは潔い。現代では稀な論理である。プロスポーツは勝ち負けのみで成り立っているから、彼の論理は明快である。
しかし一般社会では誰もこんな論理をもっている人はいない。
社会保険庁などはあれだけ何十年にわたる不祥事を起こして、歴代の長官や管理職たちの責任はどうなっているのやら。仕事を下請けに出すよう働きかけたのは労働組合だとも聞いた。彼らは責任をとらないのか?
官庁はほとんど責任をとらない。仕事と責任がかみ合っていないが、それにはそのような論理があろう。
水俣病やイタイイタイ病など公害問題の経過を見ていると、一帯誰の責任であるのか分からないようになっている。
岡田監督の辞任はもっと裏があると、今後報道されるだろうが、どんな事情があるにせよ、彼の責任をとる姿勢には拍手したい。 今日は爽やかな秋晴れであった。
杉谷 保憲 |
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「竹におもう」
|
2008. 10.
11 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「竹におもう」2008・10・11(土)曇り
参加者 山本、杉谷、高田、早川、野本、窪田、錦織、世良田、小椋、稲岡、。
川路、尾崎、池田、原、高橋、稲岡(喜)。安田。
夜来、雨は降り続いた。朝6時半にあがった。
阪神タイガースの涙であったのかもしれない。13ゲーム差を逆転されて優勝を逸したペナンとレースは珍しい。一晩泣き明かしたとしてもおかしくない。
今日の焚き火は竹林コンサートのための清掃である。雨に濡れた竹くずは燃えにくい。二つの焼却場はともに火がつきにくく難儀した。
その代わり、雨に洗われた竹は青く光っていた。美しい。
陳舜臣のエッセイ「竹におもう」は中国の文人たちの竹への傾倒ぶりを書いている。そのなかにこんな一節がある。
「日本では松竹梅といわれて、竹はお正月のめでたいものの一つとされている。それはいつも変わらぬ青さのためであろう。とすれば竹は色こそ大切であり、色にウェイトをおかねばならぬという考え方もありうる。だが、あのさわやかな青い色を用いなければ、竹の絵ではないという言い方は困るのだ。」
陳さんはそう書いて、墨絵の黒い竹にも朱筆で描いた朱竹にもそれぞれに真実があると主張している。
|
|

|

|
|
昨年より拡張された舞台
|
|

|

|
|
客席
|
|
|
|
今日、週間天気予報が発表された。それによると18日の竹林コンサート当日は“晴れのち曇り”である。
この日は今日のように、竹が光っていてほしい。
竹林コンサートは音楽のよさもさることながら、真っ直ぐな竹に囲まれていることと竹の色によって冴え冴えしていると思う。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「衝突」
|
2008. 10.
08 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「衝突」2008・10・08(水)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、早川、西村、野本、窪田、錦織、世良田、小椋、辻井。稲岡。安田。
暖かい日である。のどかであるが忙しい。
竹の学校はそれぞれが思い々に仕事をするのだが、今日は10日後に竹林コンサートを控え、お客様に喜んで
もらうための小物づくりに励んでいる人たちがいる。例えば、募金に応じてくれたお客様にプレゼントするために竹の皿やお湯飲みをつくるとか、資金づくりにモミジやコケを竹の植木鉢に植え、それを売る・・・。
残るのは舞台製作と演出だけになった。11日(土)にはすべての準備が整うはず、会員全員の参加を請う。
こうしてA竹林は竹林コンサートに余念がない。
ところが、今日も間伐が続いているB竹林に問題が起こった。例のキツネの子育て穴についてである。この16個の穴はキツネが春に子育てに使っていたが、もう使わない穴だとばかり思っていた。
昨日、「乙訓の自然を守る会」の池田さんに会ったところ、意外な意見を聞いた。この穴に軍手を見つけたという。それはキツネが習性としてくわえ込んだもので、これから秋から冬にかけてまた使う可能性がでてきたと。
池田さんは20余年、西山の野生動物を調査している。キツネが棲息していることは知っていたが、穴を見たのはB竹林が始めてで、貴重なものであるという。そしてキツネの生態を写すために無人カメラを設置したいそうだ。
もしキツネがまだこれからもこの穴を使うとしたら・・・。
放置竹林を間伐整備することは環境のために必要である。しかしそこに野生動物が棲息していると分れば、その保護のために間伐することは避けなければならない。
二つの環境対策が矛盾を起こし衝突する。
私は困惑した。
当分の間、間伐は穴から遠くで行うことにして、考えよう。この衝突をどう回避したらよいか。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「赤とんぼがいない」
|
2008. 10.
04 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「赤とんぼがいない」2008・10・04(土)晴れ
参加者 遠征組 杉谷、野本、世良田、小椋、稲岡、辻井。尾崎、原。
竹林組 高田、吉田。高橋、稲岡(喜)。林。
快晴で気温が上がった。その中を南丹市まで1時間をかけて3台の車が走った。ワラをもらうためである。今年で3年目、場所はわかっていたが、到着してみてまごついた。山間の風景は同じだが、なにかがおかしい。
去年までの田んぼが畑に変わっていた。「減反しなければならので・・・」と説明に、ああそうかとしか思わなかった。同時に、こんどの田んぼは山から少し離れているので、ヘビは少ないだろうと少し安心した。
ところがいる!いる!
「オーイ、いたぞー!」原さんが駆けつけてくる、彼女はこの種のものを見たがる。“虫愛(むしめ)ずる姫君”という言葉はあるが、爬虫類の好きな人は少ないだろうに。
畑や田んぼの畝に並んである彼岸花がやや色あせてきた。しかし去年あれほど飛び交っていた赤とんぼの姿が見えない。
すぐに気がついた。水田が無くなったことと関係がある。水の中にねむっているヤゴが赤とんぼになるのだ。そのヤゴが棲めなくなったのだ。
竹林コンサートでは今年も「赤とんぼ」の合唱が予定されている。さびしいなあ。
カエルも減った。水が無くなるとオタマジャクシもいなくなる。田んぼは採算がとれないだろうが、水田はお金に換えられない生物をたくさん生み育てて、日本の風景をつくっていたのである。田んぼで動き回っていてもなにかむなしい。
一方、竹林内では道路作りが進んでいた。ワラを積んで帰ると、トラックが竹林に上がるのだ。去年まではワラを道路に下ろし、みんなで担ぎ上げたのに、大幅な省力化ができた。
すべての作業が終ったのは薄暗くなってからであった。
杉谷 保憲
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「鳥と烏」
|
2008. 10.
01 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「鳥と烏」2008・10・01(水)曇り
参加者 山本、杉谷、高田、西村、野本、窪田、世良田、小椋。
昨日からの雨は8時半ごろ上がった。NHKの天気予報の画面は午前が雨で、午後が曇りのマークである。それなのに、このメンバーは朝のうちに雨が降り止むことを知っているかのように集まってきた。
西村、窪田、世良田さんはB竹林で伐採をする。残りはA竹林でコンサートの準備作業。
休憩時間のことだ。隣に腰を下ろした山本さんが話しかけてくる。鼻をうごめかすという表現は得意な状態を表すが、山本さんはそれに似た少年っぽい表情になる。
「中世文学を読む会」は講師の薀蓄話が楽しい会である。山本さんはその会の中心的人物だ。前回は講師が漢字の“鳥と烏の相違について”解説したという。
「杉谷さん、烏(からす)は鳥(とり)の漢字に一本横棒がないのはなぜか、知っていますか?」山本さんの鼻がうごめいている。
子どもの頃からの疑問だが、私は今も知ることができないままでいる。
「鳥は象形文字です。」
そういわれると、とりの線画が「鳥」になっていくのを思い出す。それをここで紹介したいのだが私にはパソコン力がない。インターネットで「象形文字 鳥」と検索すればたくさん見られる。
「漢字の鳥はそうしてできていますが、足りない一本の横棒は目です。目は黒い。カラスも黒い。同じ色なので、つい目を見落としてしまい、鳥に横棒が無いものが烏になりました。」
烏という漢字のなりたち ――本当のことだろうか?
杉谷 保憲
|
|
 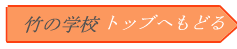
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「秋たけなわ」
|
2008. 9.
27 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「秋たけなわ」2008・09・27(土)曇り
参加者 山本、杉谷、高田、窪田、錦織、小椋、稲岡。川路、尾崎、稲岡(喜)、原。
安田由夫。安田由紀子。
今日の作業は竹炭の窯開きから始まった。
向日市からの6名とともに藤下先生の指導を受ける。 先生は 「今までで最も良質で、かつ多量の炭がつくれた」との講評。気分よくして、みんなで炭を分けて持ち帰った。
来春からのエコツァーはタケノコ掘りと竹炭作りがつなげられるかどうか。
今日はお客様が多い。古参会員安田さんが諸橋さんを、旧知の高野さんがワイズメンクラブの2人を連れてきたので、竹林の清掃作業に参加してもらった。
イヌの散歩に来たのは奥村さん。
このところ会合や取材が目白押しである。
9月25日(木)竹林関係の意見交換会(京都府庁)
9月26日(金)京都府広報課から取材
10月3日(金)コンサート演出打ち合わせ(13時30分~バンビオ)
10月4日(土)ワラの引き取り(南丹市 遠征隊長稲岡)
10月5日(日)コンサートの歌の練習(10時~中央公民館)
10月6日(月)コンサート演出の最終打ち合わせ(18時 サポセン 松井、加藤、稲岡)
10月7日(火) コンサートに協力要請の会(10時~市役所)
10月17日(金)京都府地域力と長岡京市市民参画協働との会合
10月25日(土)サポセン活動紹介展
以上に定例の作業と竹林コンサートが加わるから、“秋たけなわ”といってもよいだろう。
このうち差し迫っている来週土曜日のワラの引き取りについてはトラックの手配、乗用車の手配、参加者の確定、お金の準備などこれからのことが多いので、各位のご注意を。
(乗用車が足りないので世良田さん、小椋さんのご都合は如何?熊谷さんの健康状態は?)
井上さんが再び杖を15本つくって提供された。コンサート会場入り口に置きたい。
此の秋は 何で年よる 雲に鳥 芭蕉
杉谷 保憲
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「野球というもの」
|
2008. 9.
24 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「野球というもの」2008・09・24(水)曇り
参加者 山本、杉谷、高田、早川、野本、窪田、錦織、世良田、小椋、吉田、辻井。安田。
22日(月)に小椋、安田さんが竹林コンサートのための観客席や歩道の整備をしているので、会場は形が整ってきた。今日も作業がつづく。お客が増えることを予想して、2階席の準備、整理整頓のための焼却や場外の指示板制作など、去年より丁寧に工事がされている。
このところTVの野球観戦に時間が食われる。巨人―阪神戦で阪神3連敗、それも大敗で勝負はついているのに眼が離せなかった。
北京オリンピックのとき、各競技と野球試合をともにみていたが、ほかのスポーツは攻守が目まぐるしく展開して緊迫するのに、野球は間がありのんびりしたゲームに映った。
それにもかかわらず野球も面白い。なぜか?
野球は間があるスポーツなので、考えることができるのが面白いようだ。解説者の悠長な話し方も視聴者が次を予想する余裕に合っている。
巨人―阪神戦のように予想もしない3連敗にも、どこが悪いのか?選手か監督の作戦か?と素人でも検討できる時間的余裕がある点が野球の特徴。そののんびりのなかにどんでん返しが隠されているゲームだ。今日の今岡の逆転ホームラン(阪神―横浜)もそうだ。
阪神と巨人は同率首位。今年も残り10試合だ。しっかり視よう。
杉谷 保憲
|
|
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「竹材の未来」
|
2008. 9.
20 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「竹材の未来」2008・09・20(土)曇り
参加者 19日= 山本、杉谷、熊谷、野本、窪田、錦織、世良田、小椋。
川路、池田、原、高橋。
20日= 山本、杉谷、高田、早川、野本、窪田、錦織、世良田、
小椋、稲岡、辻井。安田。尾崎、高橋、稲岡。
3連続の出動日となるところであったが、3日目の今日が雨で中止になった。
19日は竹林コンサートの全体打ち合わせ。上記のほかに出演者、製作スタッフ、市役所のひとびとで、広範な事ごとについて検討した。
イベント専門家からみたら不思議な会議だろうが、市民が寄り合ってつくりあげるイベントは、マイクロフォンのことから駐車場のことまで、一同でうちあわせするところに意味がある。検討事項を残しながら2時間で終了した。
20日は竹炭をつくる講習会。上記のほかに向日市の6名(市民・市役所)が参加し、藤下氏(長岡京市環境政策監)の指導で窯をつかう実習。竹を燃やすのではなく炭化させるポイントや土を断熱材に利用する工夫が面白かった。
21日9時に窯を開ける予定であったが、大雨となり延期。来週土曜の9時に開ける。
タケノコから竹炭まで利用できるモウソウチクだが、その間にかつては、籠、釣竿、笛、建材、垣根材・・・など竹材として多様に利用されていた。それが現代では消失した。
いまその利用法の再構築が進められている。竹を粉砕して、肥料にしたり、ペレットをつくり燃料にしたり、あるいは食器をつくったりと研究されている。それぞれに価値があるが、どれも今後の問題である。
竹炭はすでに高い評価を受けているにもかかわらず、普及に時間がかかっている。ここでも経済性が得られないのが生産者にとっては辛いところだ。
タケノコから竹炭までの間は今後は環境材として大きな存在になるだろう。
バイオエタノールの材料として、あるいはCO2の吸収材として排出権取引(カーボンオフセットも)の対象として。その時期はさほど遠くないと思うので、これらについて勉強しておいた方がよい。
杉谷 保憲
|
|

|

|
|
|
|

|

|
|
|
|

|

|
|
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「高齢ということ」
|
2008. 9.
17 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「高齢ということ」2008・09・17(水)快晴のち曇り
参加者 山本、杉谷、高田、早川、西村、野本、窪田、錦織、世良田、小椋、辻井。安田。
先週13日はNPO設立総会と記念講演会。とどこおりなく終った。14日、15日と三連休は爽やかな天気がつづき、秋を満喫した。そのなかで小椋さんと野本さんは竹林コンサートの観客席づくりで働いた。
今日は竹林コンサートの観客席づくりが続く。それにかかる5,6人は凝り性の人で、去年のベンチに加えて、新しい工夫を凝らしている。それを支える5、6人は太陽の丘から竹を切り出す。山本さんはひとり焚き火を担当する。
昨夜は中秋の名月であった。深夜になって雲が去りさえざえとした。
空あゆむ 朗朗と 月ひとり 荻原井泉水
昨日で、私も後期高齢者の仲間入りした。後期高齢者という括りかたは幼年期とか青年期とかという区分けとは性質が違い、医療費を節約させる政策のために人生を区分けしたのだ。あつかましいというか尊大というか、世間の評判は悪い。
ところで私は若い頃から、年寄りになると人間のことがもっと分かるに違いないと期待を抱いていた。確かに若いときには分らなかったことが、高齢になって始めて分るということは多い。若いときには経験不足で理解ができないことも、人生の流れの中でいろんな事象に出会って、相対的に考えるようになり、分りやすくなる。
若年のころ内面のことは、若さという力が理解・判断力を押さえつけて超えられないことが多い。恋はその典型である。老年になっても恋ごころが無くなるわけではないが、相対的に位置づけをするから、まっさかさまに“老いらくの恋”に落ちることは少なくなってくる。
高齢になると大抵のことは分ってくるにもかかわらず、どうしても分らないことがある。それは「死」だ。これはだれも経験するが、その経験を報告することができない。“あの世”とか“天国”とかはすべて体験報告ではない。
この絶対的に知ることができないものが聳えるからからこそ、老いの心はかえって豊穣になるように思う。荻原井泉水の句はそれをよく表現している。
19日(金)13時~15時全員打ち合わせである。お忘れなく。場所はサポセン。
20日(土)炭焼きは台風接近のため無理かもしれない。そのときは一週間の順延。
杉谷 保憲
|
|
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「美女と竹林」
|
2008. 9.
10 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「美女と竹林」2008・09・10(土)曇り
参加者 山本、杉谷、高田、西村、熊谷、野本、窪田、錦織、世良田、小椋、吉田、辻井。稲岡(喜)。
安田。
京都府庁から2名の来訪があり、研修受け入れの検討があった。東大大学院の内橋氏は竹林再生作業と竹林所有者の意識変化の研究。
竹林が研修の場になったり、研究対象にされるようになったのは喜ばしい。
一昨日は総会・講演会について京都新聞に記事がでた。 昨日は竹林コンサートのポスター、チラシができあがった。そしてA竹林はコンサート会場の客席作りの一方、B竹林では放置竹林と格闘が続いている。そのほかに次の土曜日の総会と記念講演会の準備。
京都市内の書店では森見登美彦著『美女と竹林』(光文社)が平積みにされている。読んでみた。
気鋭の作家だが、 私には初めてである。奈良県出身とある。多分、 高山という茶筅の里辺りの生まれのようだ。京都大学では竹の専攻だろう。竹にくわしい。
作品は放置竹林の間伐整備が下敷きになって、妄想が展開される。奇抜な題名にも驚かされるが、妄想の内容や筆運びに仰天する。
かぐや姫を恋人にするぐらいの勇気があるのなら、一読をお奨めする。
このところ爽やかな天気はつづく。夜は特に鮮やか、今晩は半月が見られるだろう。美女は妄想の中にしかいないのに。
杉谷 保憲
|
|
|
|
|
|
✲ $$$竹林日記
$$
・・・「竹の存在をアピールせねば」
|
2008. 9.
6 山本 律
|
|
竹林日記 「竹の存在をアピールせねば」 2008・09・06(土)晴
参加者 山本、杉谷、川路、高田、尾崎、早川、野本、窪田、世良田、小椋、稲岡、 吉田、高橋、稲岡(喜)、
原、辻井、安田
毎回土曜日は参加者が多いが今日は17名という多数の参加があって、小椋さんの 指示のもと、竹林コンサートのステージ部分の竹の伐採と整理に汗を流した。
前々回からメンバーに加わった辻井さんの、作業の段取りと手際のよさに驚いた。 あとで聞くと、借地では
あるが竹薮を持っていて、竹林整備の経験があるとのこと。やっぱりそうか…。
それと、女性の腕力、といっては失礼だが、体力にも驚いた。 背丈の倍以上は十分ある、枝と葉がついた
ままの竹を抱えて、軽々と、ではないが運んでおられる。それも一回や二回でなく、何回も。
そのこととあながち無関係ではないと思うが、いま、このグループに入っておられる方たちはみな、骨惜しみをしない。こういう人たちがもっと増えたら心強いのだが… と思う。思うだけではいけない、私たちが動かなければいけない。どうしたら竹林の魅力をアピールできるか。
その意味で、「ダメもと」になるかもしれないがと思いながら、私は次の筍シーズンにうちの自治会に筍ほりの体験学習を呼びかけてみようと思っている。
一人でもよいから、竹林整備に興味と意義をみいだす人が出てくるかもしれない。
山本
律
|
|

|

|
|
竹林コンサート会場の整備
|
|

|

|
|
|
|

|

|
|
完成した竹濤亭
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「地域力」
|
2008. 9.
3 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「地域力」2008・09・03(水)曇り
参加者 山本、杉谷、高田、西村、熊谷、野本、窪田、世良田、小椋、辻井。
安田。
小椋さんと安田さんは竹林コンサートの観客用ベンチを作りはじめた。他の人はそのベンチ用の竹を伐採した。200人が座れるベンチを予定しているが、今日は5人分ほどできた。去年より手回しがいい。
京都府自治振興課から竹の学校で10月中旬から研修したいと申し入れがあった。この課は地域力再生プロジェクトを担当しているので、知らないわけではないが、まさか放置竹林で研修とは! 驚いた。行政がこんなに積極的に市民の中に入っていくとは私は知らなかった。京都府のヤルキが伝わってくる。
それにしても「地域力」とはなんだろう?優良企業があり税金をたくさん納めてくれるのは地域力だろうか?高給サラリーマンがたくさん居住して市民税を納めてくれるからそれは地域力だろうか?華々しく宣伝・広告して客を集める商店街は地域力だろうか?
どれもそれぞれ地域の力ではあると思う。でもそれは経済から見ているだけで、地域の住民の活力を見ていない。地域力とは住んでいる人々の力――人間力である。
この街には地域に尽くす人間力をもっている人が目につく。
竹林コンサートに少年少女合唱団をひきいて登場する岡田美智代さんはこう言う。「歌いっぱいの町ににしたい。街角から、窓のうちから歌が流れる、そんな町にしたい。」
そして毎月コンサートを開いている。それも午前中に。
私は何度も会場をのぞいてみた。コンサートのフィナーレはきまって観客の合唱である。童謡であったり唱歌であったり・・・。お客さんはそれを楽しみに来ているし、会場は歌を歌う満足感で満たされている。
高齢者(病弱者)を笑顔で元気づけ、配食サービスをする団体がある。先日、市から表彰された。
「おめでとうございます。」「有難うございます。これも皆さんのお陰です。」弱いものを陰から支える態度には感心させられる。
子どもたちを集めてお寺で合宿、集団のマナーを教えている人たちもいる。生徒たちに自然観察を教えている大人たちもいる。道路端の空き地にミドリを植えて手入れを欠かさない人がいる・・・みんな人間力がある。
炭鉱は石炭を掘りつくしてしまえばお終いだ。野生動物を追いやってしまえば人間が細る。年金をもらうだけでなんにもしなければ地域力は枯渇する。
地域にはいつもブツブツと湧き上がる泉源をもちたい。住民の力、「いきいき力」がその泉源であってほしい。
杉谷 保憲
|
|
 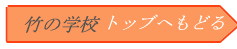
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「あずまやの名称」
|
2008. 8.
30 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「あずまやの名称」2008・08・30(土)小雨のち曇り
参加者 杉谷、高田、野本、世良田、小椋、稲岡。稲岡(喜)。
集中豪雨(1時間に100ミリも降るので、近頃はゲリラ豪雨とも言う。)による被害が全国あちこちに出ている。朝6時に皆さんにメールを発信した。「今は霧雨だが昼には止むようだから竹林に出かけよう」と。
9時にはかなりの雨でこれでは作業は無理だなと思わせた。だがその中を7人が集まった。9月13日の総会・講演会の打ち合わせをして、10時になると雨は止んだ。
早速、コンクリートブロックの運搬。それが終ると、作業はいつものようにそれぞれが思いおもいに。伐採竹の処理、サバエ刈り・・・。
稲岡夫人が華やかに声をあげた。なにか面白いことがあるのだなと近づいていくと、丈が20センチもあろうという大きな白いキノコ。多分カラカサダケだろうという。5~6本集まって生えている。
あずまやの建築が進んでいる。広さは2畳ほどで屋根も壁も竹である。内部は竹のベンチだけ。4人は座れるか。終始,工事に携わってきたのは高田さんと小椋さん。現代の名工のつもりであろうが、荒々しい数寄屋造りである。
来週は竣工だろう。それを見学に世良田さんと私が近づいた。
世良田「この小屋、なんに使うの?」
小椋 「分らん。何に使おう?名前を考えてヨ。」
世良田「茶室にしてはお粗末だし、物置にしては雨が吹き込むし・・・。使いみちもわからんのに、名前のつけ ようがないな。」
小椋 「分らん、分らん。分らんものをなんとかするのは杉谷さんがよい。」
竹林からの帰途、私は考えた。「竹濤亭」はどうだろう。「濤」は押し寄せる波である。何に使っても巧く合うだろう。
杉谷 保憲
|
|
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「生立ちの記」
|
2008. 8.
27 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「生立ちの記」2008・08・27(水)曇り
参加者 杉谷、高田、野本、窪田、世良田、小椋。
賛助) 安田。
夏休みや雨のための中止で作業がとびとびになった。今日は蒸し暑い。
小椋、窪田組が竹林コンサート用のコンクリートブロックなどたくさんの材料を購入してきた。それらを階段を担ぎ上げる。こんな日にかぎって参加者が少ないので、この労働はこたえる。汗が止まらない。
幸い賛助会員の安田さんが応援に来てくれたから本当に助かった。
竹の学校のことが「京都府だより」に掲載されて、それを見た伏見区の辻井さんが入会してきた。昭和19年生まれはこの学校では若く、心強い。
木津川市の上田さんが竹で造った食器(試作品)をもってきた。竹材の利用として可能性を秘めている。
明日28日19時30分から、NPO竹の学校の設立総会ならびに講演会の準備に入る。総会席上で、ここまでの経過報告を野本さんがする。そのために誕生のころの記録を調べた(資料作り 高田、杉谷)。以下の通りである。
2000年春、長岡京市まちづくり市民懇談会(以下まちこん)のなかで荒廃竹林の整備をしようと、竹工房・竹林整備プロジェクト(リーダー石田氏)が立ち上げられた。場所は奥海印寺バス停の近くの3反歩。6~7名のボランティアと同志社大の学生3~4名であった。
杉谷がこの年11月に参加した。
2002年石田氏が退会し、竹林整備は、まちこん4プロジェクトのひとつになり、杉谷がリーダーになった。
多分この年に、野本、窪田、高田さんが参加したと思う。
まちこんは解散し、各プロジェクトは自立して活動し始めた。その動きにやや遅れて竹林整備部会は解散し、2003年2月23日に「長岡京市竹林友の会」として独立した。(会長 杉谷、副会長 高田)
2004年春、竹林が高速道の計画地になり作業場がなくなった。 同年8月、長岡京市が斡旋し、現在の 長法稲荷社の隣接竹林4反歩で作業を再開した。
2007年には稲荷山山頂の3反歩も整備しはじめた。2006年、2007年は表彰を3つ受けた。
2008年7月17日(祇園祭の日)、「NPO法人竹の学校」が認証された。
伝統的なタケノコ栽培法の継承、水資源の涵養、シイタケの原木栽培、環境問題への啓発活動としての竹林コンサートやエコツアーなどを行っている。来月からは新しく、講演会、竹炭づくりをはじめる。
会員25名と賛助会員3名で構成している。
生立ちの記を振り返ってみると、高速道のために立ち退かざるを得なくなったとき、会員のみなさんが、早く新しい作業場を見つけてほしいと口々に云っていた、あの情熱が思い出される。
放置竹林はたくさんあるけれども、税のことなどが絡まって正規に借りることが難しく、市の斡旋はその苦労を乗り越えてできたものである。
杉谷 保憲
|
|
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「キツネの穴」
|
2008. 8.
20 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「キツネの穴」2008・08・20 (水) 晴れ
参加者 杉谷、高田、早川、西村、熊谷、窪田、世良田。
お盆休みが明けた。皆、口々に体がなまったと云う。クーラーをつけて、
TVでオリンピックを見ていたので・・・。
10月18日の竹林コンサートに向けて諸々の準備がはじまった。プログラム、チラシ、ポスターはゲラの段階。竹林では観客席用の竹の伐採がはじまった。
担当の小椋さんは、これからコンサートまでは休みをとらないと云っていたが、まったくよんどころのない事情で不参加。しかし詳細な設計図をつくってくれたので、それにもとづいて竹を切った。暑さの中で、予定の半数を切り出した。
レギュラーのタケノコ用の土壌づくりと竹林コンサートのために、しばらく放置竹林(B地区)の作業はできない。
お盆休みの間、私は放置竹林の中で発見された“キツネの子育て穴”について考えていた。
16個の横穴はすでに使われていなく生活痕もない。
もしキツネが使っていたら、私たちはどう考えただろう?
キツネを保護するために伐採を中止するか、あるいは人間のために放置竹林の整備を進めるか。
これはとりもなおさず、野生動物の保護か里山の保全かというちょっと悩ましい問題であったことだろう。
環境問題の実際は多面的に問題がおきて、全てのひとに喜ばれる解決方法はない。そのために紛糾するのが常である。
このキツネの穴はすでに使われていなかったので悩ましい問題は起きなかったが、16個の横穴は環境を考える予習問題となった。
杉谷 保憲
|
|
|
|
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「加油」
|
2008. 8.
6 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「加油」2008・08・06(水)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、早川、西村、熊谷、野本、世良田、吉田。
久しぶりにB地区(放置竹林)をカメラでのぞいた。最強のスタッフが伐採しているが、荒れ果てているので、いつごろ竹林として整備できるか見通しが立たない。8月後半になれば全員でとりかからなければならないだろう。加油!
今日は広島原爆忌。“被爆者の救済を”と民間から声が上がる。しかし政府の動きは鈍い。
私は広島・長崎のピカドンについてはかねてから疑問を抱いていた。
アメリカは「真珠湾を忘れるな」と被害者の立場を繰り返すが、広島・長崎での加害者であることには触れたがらない。ときには正当な理由があったなどと強弁する。その論理で言えば、真珠湾には日本に正当な理由があったことに思い当たらないのだろうか。
覇権をにぎると国家も人も自制心がなくなる。ソ連という国家もそうであった。今、チベットが問題になっているが、これは元を糺せば中国というより、覇権国家時代のイギリスの政策にある。イギリスが当時の清朝に押し付けたものだ。その後の中国の圧制も問題であるが・・・。
その北京がテロにおののきながらオリンピックを明後日に開催する。
がんばれ!というのは中国語で「加油!」だそうだ。燃料をそそいで燃え上がらせるという意味なのだろうか。日本語の“がんばれ”より趣旨が通る言葉だ。
チベットやウィグル族に配慮をしてもらいたい。
その上で、北京オリンピックはTVで楽しませてもらうことにする。加油!
次の土、水、土の作業はお休み。
杉谷 保憲
|
|
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「再びタラの芽について」
|
2008. 8.
2 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「再びタラの芽について」2008・08・02(土)晴れ
参加者 山本、杉谷、早川、野本、窪田、世良多、小椋、稲岡。高橋。
高校野球が開幕である。高田さんは甲子園の開会式へ。
暑い。いつも作業が終るのは11時半である。作業熱心な人が多いので、なかなかその時間に引き揚げてこない。けれども今日は11時20分には皆、日陰に入ってきた。
睡蓮の 葉の盛り上がる 暑さかな 大場 白水郎
今日の協議事項
8月9日(土)、13日(水)、16日(土)の三日間は夏休み。
9月13日(土)「NPO竹の学校」の設立総会と講演会の準備担当。
稲岡、世良多、小椋。当日は全メンバー出席のこと。
9月20日(土)9時~竹炭づくり講習。向日市環境政策課との合同。
弁当持参(指導 藤下氏)。
前回(7月30日)のこのメールに書いたが、ただ一本あったタラの木の大部分の葉がカナブンに食われてしまった。それから三日後の今日、見ると全ての葉がない。一枚もない。そしてカナブンは一匹もいなくなっている。二メートルの木が丸裸である。
自然は残酷なものだと思いながら、そのすぐ近くの乙女の丘で、私は雑草を引いていた。すると指に痛みが走る。棘である。よく見ると雑草の中にタラの幼木が潜んでいるではないか。見回すと数本ある。
なんと一本はヤラレてしまったけれども、すぐ傍に新しくタラの木畑ができるかもしれない。
インターネットでタラの木を読んだ。北海道、東北に多いが、三重県や岡山県の情報もある。長野県ではタラの木畑をつくっている人もある。
タラの芽は山菜の王様と呼ばれて、やはり天ぷらがいいようだ。煎じて呑むと糖尿病に利くとある。桜の咲くころがうまい。
来春はタケノコとタラの芽だ。こりゃ、舌がとろけるワイ。
杉谷 保憲
|
|
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「タラの芽」
|
2008. 7.
30 杉谷保憲
|
|
|
竹林日記「タラの芽」2008・07・30(水)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、早川、西村、野本、窪田、世良多、小椋。
一昨日の豪雨はこれまで遭遇したことのない激しいものだった。神戸では川で数人の死者がでた。普通考えられない事態である。
昨日は天候を危ぶみながら、11時から竹林コンサートの舞台製作のうちあわせがあった。小椋さん設計で舞台は広くなり、それにともなっていろいろ変化がある。ついでのことながら、今年は募金活動もするのでその工夫をする。
ホリの修理ができて農協から引き取った。
たった一本のタラの木が葉をほとんど食われてしまった。裸である。
見るとぶんぶん虫(野本さんの呼称、私はかなぶんといったように記憶する。)が数十匹留っている。「今年はぶんぶん虫が異常発生して・・・」と野本さん。
タラの芽は天ぷらにする。都市部の料理屋さんでは高価である。春の小樽でタラの木の群落を観たことがあるが、西日本には少ない。この芽をいつか天ぷらにできると心待ちにしていたのに。
乙女の丘で草引きをしていると、ブンと音がして眼鏡に衝突した虫がいる。叩き落としてみると、そのぶんぶん虫である。にらみつけてやった。
もうひとつがっかりしたこと。 ひとつ月前に山椒の木を移植した。
七本のうち三本は先週まで生き残った。 しかし今日はそれも枯れてしまった。土壌や水など条件は整えたが、やはり移植の難しい植物なのだ。
お盆を過ぎるとすぐ竹の伐採の予定。9月に炭焼きを試みる。これは藤下さんの指導の下に行うが、果たしてうまく焼けるのか。この夏も忙しい。
杉谷 保憲
|
|
 
|
|
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「水の音」
|
2008. 7.
26 杉谷保憲
|
|
|
|
|
竹林日記「水の音」2008・07・26(土)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、早川、野本、窪田、稲岡、吉田。
今日も黙々と除草や物置内の整理がつづいている。一つ変わったことは、雨水を受ける水槽が装置されたことである。
昨日の京都新聞夕刊は“京、25日連続真夏日”と題して、35度以上の日が連続していることを報じた。梅雨どきに降水量が少なく、その一方でプールへの人出が記録的であるという。
写真が傑作で、ヒマワリがぐったりして、猛暑と少雨を表現している。
この少雨は来年のタケノコにいい影響はないだろうなと思いながら、今日、竹林に行ってみる。入り口の花壇のアジサイ数本がほんとにぐったりしている。葉がしおれて下を向いている。
水をやった。多目にやった。そして眺めていると10分ほどで、アジサイの葉はしゃんとして元気になった。植物の水の吸収力は恐ろしいほどである。
この春から、竹に聴診器を当てて水の音を聴いている。聴診器から伝わるものはゴーという大きな音。
一人が言った。これは水を吸い上げる音とは信じられない。もしそうなら竹稈のなかは滝になっているのだろうか?と。それほど轟音である。確かに滝つぼの音に似ている。
水の音だとするならば、吸水音が空洞にこだましているのだろうか?
水の音ではないとすれば、なんの音であろうか?
竹が水を吸う力は秋冬には落ちると言う。一年を通して聴診器を持とうと思っている。
杉谷 保憲
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
✲ 杉爺の竹林日記
・・・「遺影」
|
2008. 7.
23 杉谷保憲
|
|
|
|
|
竹林日記「遺影」2008・07・23(水)晴れ
参加者 山本、杉谷、高田、熊谷、野本、窪田、錦織、世良田、小椋。
本日、竹林コンサートの助成金(地域力再生プロジェクト)の交付決定通知書が来た。10月18日をめざしてぼちぼち ――8月29日11時から舞台製作の打ち合わせ会あり。たくさんのご参加を。
葬式をどう考えるか。
私は世間で行われている葬式に疑問をもっているので、「家族葬を考える会」に2度、出席した。集まった人100人を超した。同じ思いの人が何と多いことか!
現代では、家の畳の上で死ぬことは事実上できず、病院のベッドで死を迎えることになることをはっきり認識しておかなければならないという。私はまずその点から漠然としていた。
その時に至って、病院で延命治療を断るのは当然と思っていたのだが、これにも難しい手続きが要るので、いい加減な話で済ましておくことはできないそうだ。
家族葬は安上がりなのか?現行の葬儀屋による葬式代よりは安いが、思ったほど安くはならない。
ウェディングドレスを着せてもらって焼き場に入りたいと死者が希望していた場合は・・・
遺骨はどう扱うか・・・庭に埋めてはならないが撒いてもいい
この程度は初歩段階のことで、死は難事業であることがわかった。
今、すぐ準備できることを教えてもらった。それはまず遺影をつくっておくことだという。
それなら私はすでに準備している。竹林を背景にした写真で、今も机の上に飾っている。
しかし撮り直ししたい気持もある。竹をもっと若いものに代えたいのである。
変なことだ。なにを考えているのだろう?
杉谷 保憲
|
|
|
|
|
|








